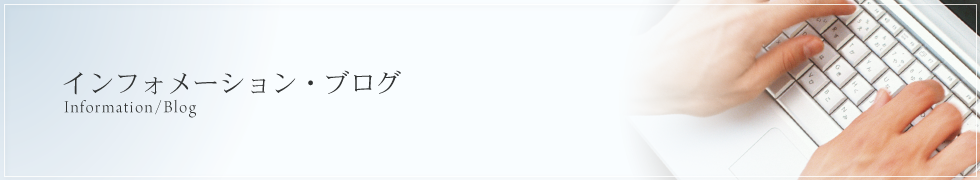利己的遺伝子が集団を作って、共同体として生き延びることを図った最小単位が細胞である。細胞は分裂して増えるが、その時自己複製子も複製されて増える。有性生殖では、二つの個体由来の自己複製子の集団が受精によって混ぜ合わされ、補い合って有利に働く。
二つの集団が混ざり合い、つながり合って複製子は改良され、有利になった自己複製子が生き残る。ゲノムの中に大量に含まれる無意味な配列はそうしたエリート集団の離合集散を助けるが、それ自身は単なる落ちこぼれの寄生者、あるいは集団にとって何の役にも立たない旅人に過ぎない。しかし、如何に複雑で精巧な乗り物を作ったとしても自己複製子の利己的な本性は変わらない。それは、複製し、生存し、拡大するために乗り物を徹底的に利用する。その乗り物が早死にしないように指図し、不利な条件でも生き残れるように性による遺伝子の交換を可能にした。動物の性行動には、良好な自己複製子を何とかして絶やさないで生き延びさせるための戦略が現れているという。アリのように、自分を犠牲にしても種の存続のために働き続け、親鳥が子供のために自分を危険にさらすのも、みな自己複製子としての遺伝子を生き残らせるためなのである。
こうしてドーキンスは、新しい「DNAの思想」として、生物は遺伝子の作り出した「生存機械」に過ぎないという考えを打ち出した。彼の理論は、さらに進化論や動物行動学の領域にまで及び、最終的には、DNAとは異なる自己複製能力と生存志向を持ったミームという文化伝達の単位を考えて終わる。人間の文化は、文化伝達あるいは模倣の単位であるミームが、同じように利己的に増殖して形成していくものだという。ミームもまた遺伝子と同じく不死身である。
しかし、遺伝子のあくまでも貧相な自己複製欲を見てしまった上では、ミームという文化因子などは生物学的な説得力を持たない。ドーキンスの利己的遺伝子説は欧米で論議を呼んだが、本当に人間は遺伝子の乗り物なのであろうか。
ドーキンスの考えている遺伝子は、最終的にはタンパク質に翻訳される何らかの意味を持った単位である。しかし、ゲノムの中ではそんな働きが認められない、いわば無意味な部分の方が多い。こうした余分なものは、寄生者として生存機械に乗せてもらっている無害だが役に立たない旅人に過ぎないと考えていた。
しかし遺伝子の解析が進むに連れて、この無意味な配列の中に、様々な働きが存在することが分かってきた。例えば一見無意味に見えた繰り返し配列が、遺伝子同志をつなぎ換えたり、転写を変更させたりして、もとの文章とは違う意味を作り出すのに役立っていることが分かった。DNAとして書かれた文章を、タンパク質に翻訳する前段階として、それをRNAに転写するという作業がある。転写の部位を指定したり調整したりするような構造(それ自身ではタンパク質になるものとならないものがある)も数多く見つかってきた。転写を制御しているタンパク質が多数コーディネートして微妙に情報を呼び出し、かつ修飾している一段と複雑な機構が見えてきたのである。
あちこち飛び回ってもともとの遺伝子の意味を変えてしまうようなDNAも見つかってきた(トランスポゾン)。ドーキンスが最初に規定した、かたくなで自己複製のみを目的としたDNAとは違った、しなやかなDNAの姿が見え出してきたのである。
典型的な例は、免疫系の遺伝子であろう。免疫細胞のうちT細胞とB細胞は、「自己」以外の侵入者、あらゆる「非自己」を識別するためのアンテナ、レセプターというタンパク質を持っている。様々な「非自己」を認識するためには、それに一つ一つ対応できる受容体がなければならない。様々な「非自己」由来の物質(抗原)と、それに個別的に対応する受容体の構造は、しばしば鏈と鏈穴の関係に例えられる。