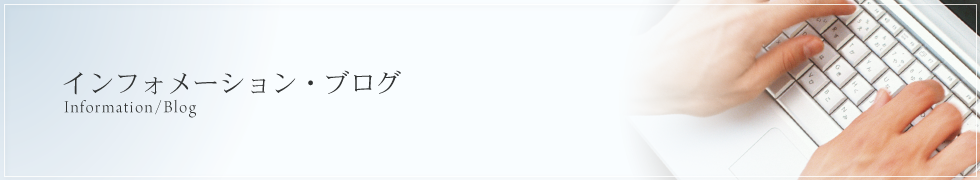DNA複製と読み取りの基本的なルールは、生物のすべてを通して同一である。遺伝子の発現機構の研究でノーベル賞を受賞したジャック・モノーは、「大腸菌での真実は、象でも真実である」という名言を残したが、DNAという物質自体も、それが生命活動を指定していくルールも、相手がカビであろうとうじ虫であろうと人間であろうと同じである。極言すれば、人間と葦の違いは、DNAの配列の違いである。
この事実を、西欧社会はどのように受け止めたであろうか。キリスト教世界では、海を泳ぐ魚、地を走る獣など、この世のすべての存在を支配する権利を、人間は神から保証されてきた(創世記)。神によって選ばれたはずのその人間が、基本的にうじ虫のそれと同一のルールにしたがって創造されていたのである。遺伝子の研究、ことにそれを物質的に扱う生命科学技術に、常に暗いイメージがつきまとい、未だ正面切った社会的発言がややもすると控えられてきたのには、そのような背景があったためではないだろうか。
一方東洋、ことに仏教を伝統とする日本などは、この事実への抵抗があまりないのではないかと思われる。「草木国土悉皆成仏」という言葉が「法華経薬草喩品」にある。草も木も、塵泥にいたるまで、生命のあるものはすべて平等という意味である。その観点に立てば、DNAの普遍性を受け入れるのに何一つ抵抗はないはずだ。
造物主DNA論には、もう一つの側面がある。それはニワトリの卵からニワトリが生まれ、へビが生まれることはないという、種の個別性の問題である。実際には種のみならず、亜種も変種も、さらには一つ一つの個体の特徴、人間では個人の特性などもDNAで決定されている。その決定にしたがって生を受けた生物体は、DNAの記号を子孫に伝えて死ぬがDNA自体は永遠に滅びることはない。そこから第二のDNAの思想が生まれる。
1970年代に入るとDNAの構造解析の技術が進み、DNAの様々な行動様式が明らかにされていった。DNAの行動様式などと擬人化しなければならない理由は、それが当初考えられていたほど単純なコピーマシンではなく、狡猾な戦略を使って、生物の行動、進化や適を含む社会生物学的な現象に至るまでを規定していることが分かってきたからである。DNAを疑人化する事で30億年以上に作り上げた生命戦略が見える。
これを考える前に重要な事実を指摘する。まずはタンパク質として最終的に翻訳されるDNAの配列構造(エクソンと呼ぶ)は、人間のような高等動物では、その個体に固有なDNA全体(ゲノムと呼ぶ)の2~3%に過ぎない。後の部分には、タンパク質には翻訳されないが、DNA暗号翻訳のスイッチを入れたり切ったり、読み方を変えたり、複製を制御したりするような調節性の働きを持った部分も含まれるが、他の大部分は何の役にも立たない無意味な文字が並んでいるだけである。その中には、昔は遺伝子として作られたが、働く事なく死んでしまった遺伝子の死骸も含まれる。意味のある文章は、膨大な無意味な記号の大海に点在する小島のように見える。
この無意味な部分がなぜ存在するのか。例えばゲノムの中に大量に含まれている繰り返しの無意味な配列の多くは、先ず一つの鎖の無意味な配列ができ、それが細胞の中で無意味なコピーを増やして拡がってきたものらしい。タンパク質として読み取られる部分が離れ離れに存在していて、その間にわざわざ無意味な配列(イントロン)が入り込んで、最終的な翻訳作業のときにわざわざ切り捨てられるというのもある。こうした無意味で冗長な配列は、あちこちの似たような部分とくっついたりして、ゲノムの安定性を乱す原因ともなるが、一方ではゲノムがダイナミックに変化するために重要な役割を果たしてきた。
もう一つの事実は、一部の遺伝子は後天的に変化するということである。免疫系では、無限といってもいい様々な異物に対応できるタンパク質を作るために、遺伝子の断片をつなぎ合わせて、新しい遺伝子を作り続けている。断片と断片の間には、読み取られないDNAの配列があるが、そこに含まれる小さな回文状の構造のおかげで、読み取られるべき断片のつなぎ換えが有効に起こるのである。
こうして膨大な量存在する無意味な配列のDNAも、細胞が分裂する際には忠実にコピーされて二つの細胞の中に入っていく。細胞自身にとっては何の役にも立たないのに、コピーを作って自己保存だけはしていると言う意味で、L・E・オーゲルと、F・クリックによって「利己的DNA」という言葉が作られた。この事実を拡大して進化論と動物行動学の観点を加えて発言したのがリチャード・ドーキンスである(「利己的な遺伝子」1991年)。ドーキンスは、視点の変革を訴える。ダーウィン以来、進化は自然淘汰と適者生存によって行われてきたという。しかし適者というときの主体は何なのか。生存を争っているのは種ではなくて、本当は遺伝子なのではないか。これがドーキンスの主張である。ドーキンスによれば、本能的に自らのコピーを増やし、自分を生き延びさせようとしているのは遺伝子の本性である。その遺伝子たちが、自分にとって有利な乗り物として作り出し、進化させてきたのが生物の種なのである。人間もまた、遺伝子が、自分が生き残るためにプログラムした、使い捨てのロボットに過ぎない。ドーキンスは、遺伝子の最も基本的な自己複製という属性をとらえて、その企みの主体を「自己複製子」と呼ぶ。生命の誕生はたった一度、自己複製子が原初地球のスープに生まれた時だ。
最近では、最初の自己複製子はDNAによく似た分子であるRNAだとする説が強いが、それがDNAであってもRNAであっても、あるいは全く別の物質であってもかまわない。その構成要素に相補的に結合できるものが周りにいくらでもあり、それが次々に結合していけば、最終的には逆のレプリカができる。そのレプリカはまた相補的に結合する要素を連ねて、もとと同じものをいくつでも作っていくことができる。
例えば7個の穴が開いているアルミ板があったとする。それを沢山の未加工のアルミ板の中に投げ入れると、最初のアルミ板と同じ形の7つの穴の開いたアルミ板が自動的にできてくるという機械が在れば、それは自己複製子の機械である。
この自己複製子は、次々に自分を忠実にコピーしていくが、時には間違いを生じる。少しずつ違ったコピーができると、それらが集合し、つながり合って、複雑なゲノムを構成するようになる。ゲノムは、コピーを増幅し、やがて自分が乗り込むべき精巧な乗り物である生物体を作り出し、それを進化させることによって自己複製子の生存と拡大を図る。
人間もまたその乗り物の一つに過ぎない。