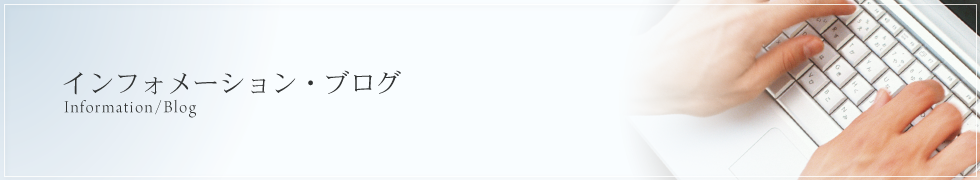胸腺は胸腔内にある腺状の構造を持つ組織で、心臓の前面に張り付いたように存在する小さな臓器である。胸腺ほど老化の影響を受ける臓器はほかにない。大きさから言えば、十代で最大の35グラムほどになり、後は年齡とともに退縮していく。実質的には、出生前から出生直後にかけての方が、ぎっしり細胞が詰まって増殖している。おそらくその時期こそ、胸腺の中で「自己」が確立していく時だろうと考えられている。
免疫系は本来、「自己」を攻撃したり排除することはない。これを「自己寛容(卜レランス)」と呼んで、免疫の重要な属性としている。しかし、あらゆる「非自己」に対しては、容赦なく排除の反応を起こすのが普通である。免疫というのは、もともと「自己」に対しては寛容なのに、「非自己」に対して極めて不寛容な態度を示し、例え親子や兄弟の間でも移植を受け付けない。自己に対する寛容が破綻すると、免疫細胞は際限無く自己を破壊し排除しようとする。それが自己免疫疾患である。しかし、ある種の非自己に対しては、免疫系が寛容になってしまうこともある。例えば肝炎ウイルスなど、もともとは非自己である病原微生物に対して、免疫反応で排除するのではなく、逆にそれと積極的に共存してしまうのである。肝炎という病気は、肝臓の細胞内に寄生したウイルスに対する免疫反応が、感染した肝臓の細胞を傷害するために起こる病気で、寛容になってしまえば肝炎は起こらない。ウイルス性肝炎について見れば、ある人は初めから寛容になってウイルスと共存する道を選ぶが、別の人は強烈な免疫反応を起こして致命的なまでに肝臓を破壊してしまう。また一部の人は、寛容となってウイルスと共存しながら、時々思い出したように反乱を起こして、慢性の炎症を起こす。それぞれの人が、異なったタイプの反応性を選んでいるのである。日本国民15%が、杉の花粉に過敏症を持っているという。同じ空気を呼吸しているのに後の85%はアレルギーを起こさない。寛容になっているからである。なぜある人に対しては寛容になり、またある人には排除反応を現すのかについては未だ不明な点が多い。現代免疫学の最大問題である。免疫学は、個別の反応性がどのようにして作り出されるかについて、様々な非自己に個別的に対応しているが、体個性の原因追究が課題である。
ある生物種の個体の聞でDNAを比べてみると、興味をそそる事実が分かる。個々のDNAの間に違いがあるのである。例えば人間では平均500塩基対について一箇所の違いがあり、それらはDNA分子に沿ってランダムに分布している。これらの違いは突然変異(一つの塩基が他のものと入れ代わること。一つまたはそれ以上の塩基の欠失または挿入)、短いDNAの再配列(転位や再構成)などの結果であるが、大部分は突然変異である。このような変化はDNA鎖の全長にわたる標識マーカーのようなものなので、遺伝マーカーと呼ばれている。
このようなDNA配列の変動が起こるメカニズムは様々である。多くの化学物質、X線のような放射線、紫外線などは突然変異原である。DNAの複製自体も変動の原因になりやすいきわどい過程である。有糸分裂や減数分裂の際に親DNAのニ本鎖はその片方ずつが鋳型となって新しいニ本鎖を作る。その結果できた細胞(有糸分裂でニ個、減数分裂で四個)は親細胞のDNAのコピーを持つことになる。