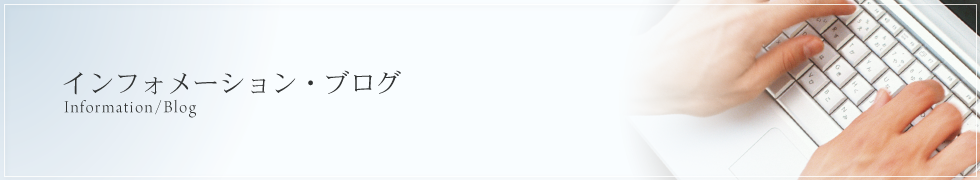どんな医師でも、一人一人の患者について、苦心惨憺して正確な診断をつけ、正しい診療を行おうと努力しても、なお、剖検(病理解剖検査)により病屍体を限りなく探索すれば、誤ちは幾らでも見出せるものである。
誤診とは、例えば、肝職が腫れて大きく成っており、それが癌による病変であることが臨床上に診断され、それに対する治療に専心して、結局、死亡して、剖検して診ると、肝臓の所見は、医師の臨床診断の通りであるが、胃の一部に予想していなかった小さな潰瘍が見付かったとした場合。
それを顕微鏡的に検査したところ、癌細胞が発見され、病理解剖学的に肝臓の癌はこの胃の小さい癌病巣からの転移であると診断された場合、これは、医学的には主病巣と転移病巣の判断を誤ったもので、立派な誤診と言うことになる。
臨床的に、胃の小さい癌は発見しにくいこともあり、また直接の臨床症状には成っていなかったとも考えられ、一方、転移した肝癌の方が一方的に成長悪化したもので、臨床症状の殆ど全部が転移性肝癌によって表現されていたと考えてよいものである。
したがって、臨床上では医師が患者の処置に大きな誤りを犯していたということには成りにくいものと言ってもよい。
こうした場合でも、医師はあくまで病巣、病変を徹底的に臨床の段階で補足し、理解することを終局の目的としているわけで、厳密には誤診と言うことになる。
誤診ということを考えた場合に、それには、究極は剖検による病理学者によって冷厳に研究されることが必要である。
医師が患者を診断し、治療して、治癒して行くということは、臨床上では喜ばしいことであるが、この場合でも医師の判断が医学的に必ずしも正しかったと言えない場合もある。
医師の判断が誤っていた場合でも、病気が自然に治癒に至ることも決して希ではない。
また、外科医が手術をし、病巣を目で見た場合ですら、後で剖検した機会に、病巣臓器を誤認し、病変の種類を誤って認識していたことが発見されることがある。
さらにまた、病理学者が死後解剖し、病巣部位を確認し得ても、病変の種類、病変の原因を確定し得ないことすら、希にはあるのである。
このように、病気の実態を完全に把握することは至難なことなのである。これが臨床医学の真相であり、困難さであることを、私たちは理解しなくてはならない。
もちろん終極的診断や治療の結論は、医師の判断に任せざるを得ないが、それに対して、正診とは、内容についての知識の中で、その診断や治療に誤りがなかったかの判断は、患者本人が、治療と治癒の責任者と言う意識によって、改めて判断すべきであるかもしれない。
それは誤診と正診の違いについて、予めその知識について学んで置く事が必要なことかも知れない。
それには、診療にあたった医師が病気に対して、学的に如何に真摯に立ち向かっているかの態度を観察することから始まるものである。
それは、担当医師が、真剣に疾病に取り組めば組むほど、その医師の考え方が、こちらに伝わって来るものでなければならない。
これは医師への酷な思いかも知れないが、医師が自分の行った診療行為に責任をどのように感じ、反省しているかの第三者判断の目安となるものである。