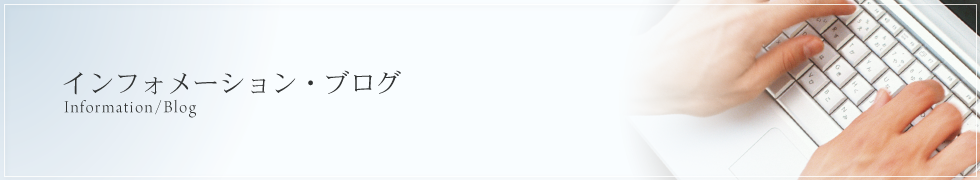遺伝的マーカーの存在は進化輪の支えとなる。進化論はイギリスの博物学者チャールズ・ダーウィンが1859年に出版した「自然淘汰による種の起源」という論文の中で初めて唱えた。遺伝的多形性によって各個人の遺伝子には数多くの変動があるが、この変動は一定の方向に向かって連続して起こっているとダーウィンは考えた。生殖率が食物資源の供給より大きくなると、生きるための争いが起こり、弱いものが死に、適応したものが生き残る。何らかの遺伝的な変化は有利に働き、その他のものは不利に働く。有利な性質を持ったものが生き残るように働く過程が「自然淘汰」である。一連の環境条件の下に、遺伝的に出来上がった個体は特定の表現形質を示すが、この特性は個体の生存のために環境に適応する必要がある。ほとんどの遺伝的変動はわずかな変化に過ぎず、はっきりと優位性を示すには不十分である。このような淘汰に対しての優位性は方向性を持つ進化の過程で現れる。つまり、進化の流れが助け合って、数千年の間に同じ定方向性を示すのである。したがって個別の変化よりも、定向進化が生物的進歩の本質的な因子である。これが一般に認められている進化輪の主な筋道である。しかし、まだ生物学者の中では大きな論争がある。DNAの変化は確率の法則にしたがって偶然に起こるのか、または進化の機構の根底にある淘汰の圧力を通して予め決められている設計書にしたがっているのだろうか?
実際にはこの両者が混じり合っていると考えたほうがよい。突然変異はゲノムの中でランダムに起こるが、淘汰は環境を通して働く。この関係はジャック・モノーが1970年に書いた「偶然と必然」という本の表題によく表されている。しかし、突然変異は必ずしもランダムに起こるわけではない。ある方向性を持った突然変異生成の例が証明されているのである。人間のゲノム中で二つの塩基CとGが連続している頻度は、統計的に予測される頻度より少なく、またこのCGと二つの塩基がつながっている場所ではメチル化が起こりやすい。このことは何を意味するのであろうか。DNA分子の中のシトシンには時々メチル基が着くというちょっとした化学的修飾が起こる。このメチル化が遺伝子の発現に影響を与えると考えられている。全部のシトシンがメチル化されるわけではなく、そのあとにグアニンが着いた場合にだけメチル化されるのである。このメチル~シトシンは更に二次的な化学修飾を受け、もう一つの基であるアミンが取れて酵素が入る。この場合、メチル~シトシンからアミンが取れて酵素が入ったものはチミン(T)であることが重要である。このようにCがTに変わることは頻繁に起こり、この変化はDNAの制御・修復機構を免れるらしい。したがって、CGはメチル化の頻発する点であると同時に、突然変異を頻発させる点でもある。科学者の中には、このことが特定の筒所で突然変異を増加させる庄力を生む機構の一部であるに違いないと思っている者もある。一方、中立説を信奉する科学者たちは、偶然のみが作用すると主張している。
分子生物学者が発展させた理論は、実験的な証拠によって裏付けされており、進化の機構に関する現代的な解釈を強化することになった。ほとんどの個体のDNAの変動は非常に小さいので、それと表現形質との間には因果関係は見られない。したがって、自然淘汰の制御から免れている。そうであるとしたら、自然淘汰ではなく分子遺伝学の法則によってもたらされる何らかの選択圧の存在を認めなければならない。多くの科学者の意見によるともっとも適合したものではなく、もっとも幸運なものが進化の過程で生き残るのである。
このように進化の過程についての概念が変わったことによって、「ダーウィンの進化論が疑問視される」とか「ダーウィン主義の崩壊」などという扇情的なタイトルの派手な新聞記事が現れたことがある。しかし、ここは冷静に考える必要がある。地球上に生息している生物の種や、かつて生息していた生物の種の間の系統関係を明らかにするためには、ダーウィンの進化輪は依然として、全体を概観するもっともよいモデルなのである。本質的にはDNAの研究によって、1859年に体系化されたこの理論の一部は改良されなければならないが、他の部分は改訂であるに過ぎない。