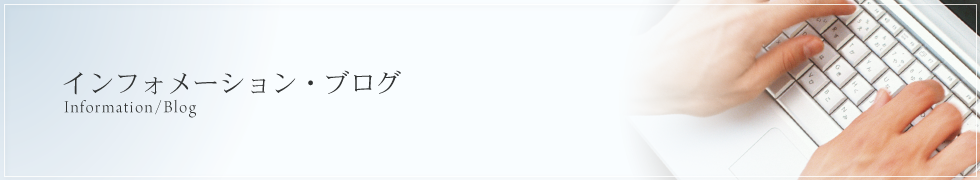胸腺が退縮するのにやや遅れて、T細胞系の免疫機構の低下が起こります。T細胞に依存した抗体の生産能力、がん細胞などを殺すキラーT細胞機能、ヘルパーT細胞機能などが、だんだんと低下します。『非自已』に対する様々な反応性は、遅かれ早かれ低下の一途をたどるのです。
ところが、『非自己』に対する抗体の生産能力が低くなるころから、『自己』の様々な成分、例えば『自己』の細胞の核と反応するような抗体が作られ始める。すぐに病気を起こすわけではないが、『自己』の赤血球、甲状腺、ガンマグロブリンなどと反応する怪しい抗体が出始めるのです。実際目的にかなった抗体を作り出す能力が低下したのにも拘らず、血清中の免疫グロプリンの量は年齢とともに上昇します。IgGやIgEを生産するような細胞の数は、70歳代では青年の2倍以上にも増えています。つまり、ここで反応しているB細胞は、基本的には無意味か、あるいは『自己』と反応するような好ましくない免疫グロブリンを作っているのです。インフルエンザに感染したとき、うまく中和抗体を作ることができなかったのはこのためです。
T細胞は、自分と異なった組織適合抗原(MHC、ヒ卜ではHLA)を持った細胞に出会うと、それを『非自己』と認めて分裂増殖し、インターロイキンを出したり、直接それに取り付いたりして『非自己』を排除するように働きます。
この反応の現場を見るために、T細胞を分離して、他人のリンパ球、すなわち『非自己』の細胞と混ぜて培養するという実験があります。混合リンパ球試験(MLR)と呼ばれるこの反応を利用すると、T細胞が微細な『非自己』を見分け、DNAを合成して増殖するありさまが観察されます。『非自己』の代わりに『自己』のリンパ球を混合してやっても、T細胞は全く反応しないのが通常です。
若い動物のT細胞でこの実験を行うと、刺激がない状態では全くDNAの合成は起こらないが、他人から採った『非自己』のリンパ球を加えていくと、劇的なT細胞の分裂増殖が見られます。MLRが始まったのです。
ところが老化動物のT細胞で同じ実験を行うと、刺激を与えないにも拘らず分裂が始まり、DNAの合成が起こって来ます。そこに、『非自己』のリンパ球を加えて刺激してやっても、ほんのわずかしか反応の上昇が起こりません。すなわち、老化動物のT細胞は、刺激がなくても興奮状態にあり、刺激を与えたからといって的確に反応できないのです。この興奮状態というのは、恐らく、常に『自己』の成分、ことに自己のMHCと反応し続けているためであろうと考えられています。
もともと免疫系では厳格に禁止されているはずの『自己』との反応が、どうして生じてしまったのか。その度応によって作り出されてしまう多目的分子インターロイキン群によって、免疫系にどのような混乱が生じるか。何故『非自己』に対する正確な認識が失われてしまったのか。免疫超システムの自己同一性を失調させたのは何であろうか。