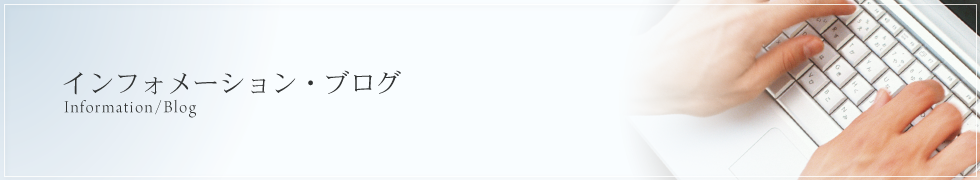発生初期の過程は、どの生物でも驚くほど似ています。人を含む啼乳類は、受精後発生のごく初期から、胎盤という、『保護装置』を作り、その中で形を作り上げます。鳥類や両生類は卵の中で発生するという違いはありますが、それでも体を作り上げる過程そのものは似ています。だから、発生の段階に応じて使いやすい生物を用いて、色々な知見を得てそれらを総合して全体像を捉えるという研究方法がとれます。
もっと発生の初期の方、つまり細胞がようやく固まり『あるいは袋』の状態から次第に体の作りの基本を行っている頃の問題には、ショウジョバエなどを使えばわかりやすいと言うことになります。その結果は発生のプログラムで働いている重要な遺伝子群や、それらの調節の仕組みが、少しずつ明らかになりつつあります。
発生プログラムでの調節の特徴は、ある時点から不可逆的になるということです。つまり、特殊化してしまった細胞は、原則的にはもう他の細胞になることはできません。そう言っても、ある程度の融通性が在り、例えばイモリのように再生をする生物もいます。再生は、発生を考えるための素材を提供してくれるので、分化決定と融通性の喪失とが分かちがたく結びついているのが解ります。
発生過程では遺伝子そのもの、もっと正確には、ゲノムDNAには変化は起こらないのが原則です。一つの個体を作っている細胞はすべて一個の受精卵からできたものであって、まったく同じ遺伝子のセット(ゲノム)を持っています。このように同じゲノムを持つものをクローンと呼んでいます。もともとは、個体について使われていた語ですが、同じゲノムを持っている細胞もクローンと呼び、最近ではDNAそのものをたくさんふやした時もやはりクローンと呼んでいます。
植物では、動物と違って、分化した細胞からもう一度個体を作ることができます。さし木や、さし芽がそれです。タバコやニンジンでは、葉、根、花粉などそれぞれに分化した細胞を小さく刻んで培養して、一度脱分化(特殊化した機能を失うこと)した細胞に戻し、改めてもう一度分化させて葉や根を作らせることができます。たった一個の細胞から出発して完全な個体を作るというドラマチックなこともできます。これは分化した細胞も遺伝子系として全ての可能性を保っている、つまり全能性のあることを示しています。