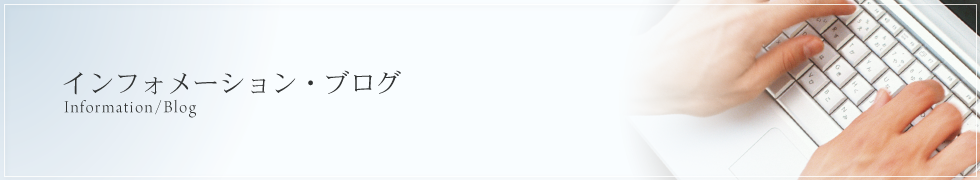卜ロフィック説を支持する知見は、未だ不十分である。それゆえ、ここで述べられたトロフィック機構に関する諸説の一部が当を得たものではなく、または単に間違ったものであっても驚くには当たらない。しかしそれらが曖昧なものであっても、神経結合がトロフィックな相互作用に基づくという普遍的な概念の評価が下がることはないと思われる。ニューロンと標的細胞間の結合は、細胞間のシグナルによって調節されていると結合するよりほかはないだろう。この事実を認識することは神経生物学での実験的、理輪的な問題へのアプローチの仕方に影響を与えるに違いない。そしてまた知覚、認知、知能や人間に特に関係のある他の精神作用の最近の仮説では、脳が無用の長物として体の中に宿っていることを認める傾向にある。トロフィック説は、神経系が標的の変化に対応することに立脚しており、脳を解明する第一歩は脳が体からの要求をどのように満たしているかを理解することにある。
それではトロフィック説の挑戦点を終わりにまとめて記述し考えの材料にしたい。
トロフィックな相互作用で神経結合が変化することを支持する知見は、シナプスの伝導効率に関与する上の研究や、神経系の長期間変化がニューロンの遺伝子の活性に基づくという考えを超えることができるだろうか?といった点から考えると、トロフィック機構は反射行動における神経結合の短期的変化には関与していないらしい。しかし、トロフィック機構によって神経結合が徐々に変化することは、神経系が体について学習する繰り返し更新される記憶に相当する。
一方、発生期に最初に出来る神経結合は、ある動物が将来遭遇する環境について学習することの記憶に相当している。この種の徐々に起こる学習の原理は解明出来る。生体の内外の環境が神経発生に一般的に求めるものは完全に予測されるが、大きさや形の変化する標的が神經系に何を要求するかを予測することは不可能である。すなわち、生体の内外で起こる変化に対し、学習する目的は同じであり、それは未知の境遇に対して適切な神経機能を発揮できるようにすることである。
学習の神経機構に関し、シナプスの伝達効率を変える機構と平行して作動する、トロフィックな相互作用に基づいた、学習における細胞及び分子機構を想定出来る。この考えに従うと、特定の遺伝子が活性化することで神経系の変化が恒久化すると考える必要はない。
また、この変化が遺伝子に組み込まれるということもない。トロフィックな相互作用による神経系の変化には、ほかのいかなる細胞機能よりも遺伝子の重要性を認める必要がないのである。トロフィック説における恒久性とは、神経の結合パターンの形態にある。この結合パターンは平衡状態にあり、神経結合はダイナミックな平衡状態を保ちながら新生しかつ退行している。この平衡状態を生み出す力は、標的の大きさや形が変化すること、卜ロフィック物質の生産やそれに対する感受性(例えば、それらは加齢で変わる)、標的細胞の形、競合する軸索終末間での電気活動の時期と量などである。
以上のように、神経伝達物質の活動によつて誘究されるシナプスの伝達効率の短期的変化と、トロフィックな相互作用によって誘発される神経結合の新しい変化は明らかに相違しているが、これら双方に関連性がある。行動または電気生理学的所見から判断すると、シナプスの伝達効率が上昇していると活性部位の数と大きさが増大し、その逆も起こっている。パリコーシティ(活性部位のある終末分枝の膨らみ)の数もシナプスの伝達効率の長期的変化に平行して変化し、短期的変化から長期的変化への過程だと考えられる。